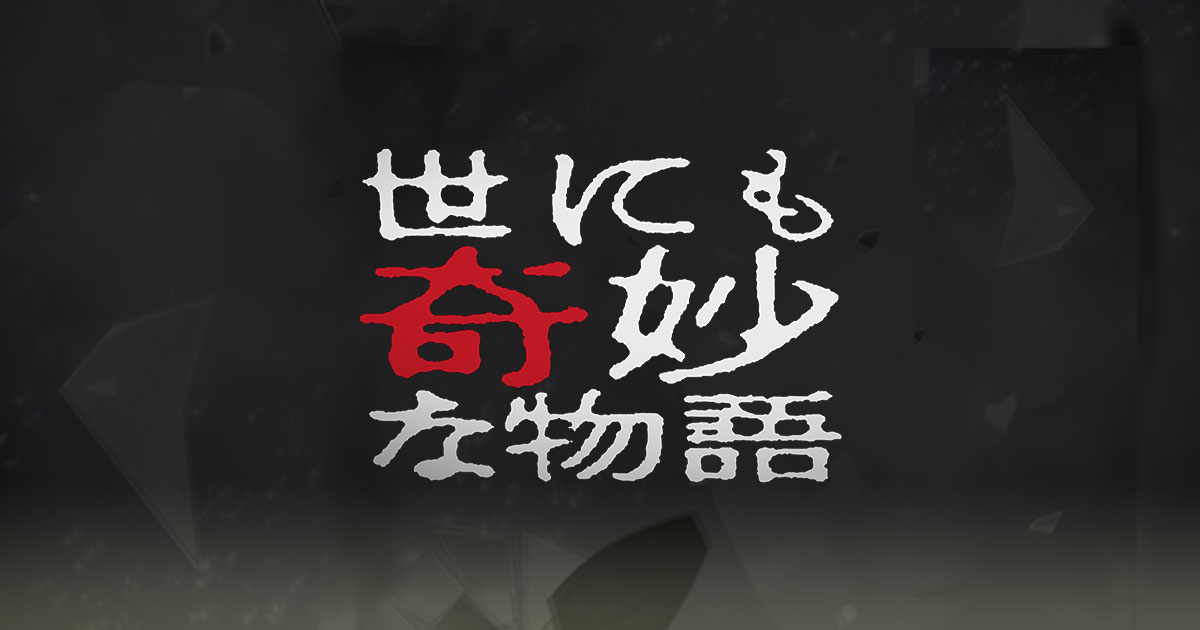
皆様ご存じの番組、フジテレビ「世にも奇妙な物語」。35周年記念として2025年5月31日に最新回が放送されました。筆者の私も、企画会議なる所謂作品コンペに何度か参加させていただいた経験がありまして、200を超えるアイデア・企画書・プロットを考えて提出。今回は、番組プロデューサーさん含め、「世にも奇妙な物語」という番組が、どのような企画意図を持っているのか、どのような作品が求められているのかというお話をしていきたいと思います。特に、ホラー作品を書いているという脚本家のみなさまの参考になりましたら幸いです。
ショート作品の一般募集もありました
私の記憶では、5~6年前くらいとおもいますが、「世にも奇妙な物語」の公式エックスをメインに、世にも奇妙な物語のショートストーリー(アイデア)募集を行っていました。それも確か、最後まで完結していなくてもOKで、オチまで付けなくとも、150字以内で説明できる設定や世界観だけでも良いということだったかと記憶しています(間違っている部分もあるかもしれません)。私が確認したところ、現在2025年7月時点ではそういった一般応募は見当たりませんでしたので、もう終了してしまっているのかもしれません。もし情報をお持ちの方がいましたら訂正・ご指摘してください。
フジテレビ「世にも奇妙な物語」公式エックスアカウント
フジテレビ「世にも奇妙な物語」過去回ボットアカウント
過去に放送されてストーリーを検索することができるエックスボットアカウントです。
近年、公式サイトや公式SNSのコメントでも「名作が生まれていない」という声が良く見受けられます。なぜ、名作と呼ばれるものが生まれにくくなっているのでしょうか?その要因を考えていきましょう!
基本に立ち返る制作陣の意図
当番組の25周年あたり、10年前のプロデューサー陣が希望されていたのは「原点回帰」でした。しっかり組み込まれたホラーとミステリー、奇妙な物語、人間ドラマ。これに立ち返ってみよう。ということだったと記憶しています。そこから、過去の名作を今一度掘り下げて見返していくという作業を私個人としては繰り返していました。番組自体も、それまでのフォーマットから少しずつ変化をつけていました。というのも、10年前までは、短編ホラー(10分前後)2本、不思議系(10分前後)1本、感動系(10分前後)1本という番組構成フォーマットが主流でしたが、ショートホラーという枠を設けて、短編、中編ストーリーの合間合間にブリッジ的に1分で完結するショートホラーを挟んで番組全体のボリュームを出す試みがありました。また、過去の名作をリメイクしてスペシャル番組として放送した回もありました。所謂、その時の若者視聴者をターゲットとした構成にしたという意図があったのだと思います。古くから観ている世代も新しい世代も「世にも奇妙な物語」を新鮮な気持ちで視聴できるという狙いがあったということでしょう。
それだけではなく、昔から現在でも続いている(と思われる)ことで言うと、「世にも奇妙な物語」で採用される作品は全てオリジナルということではないということです。短編を得意とする星新一氏であるとか、手塚治虫氏、藤子・F・不二雄氏の短編作品を原作としたエピソードもありました。勿論、新しい作家やクリエイターの作品を原作としたエピソードやシナリオコンクールで出品された作品をベースに番組仕様にリメイクされたパターンの作品もあります。
番組の企画募集会議(コンペ)では、原作モノでもオリジナルでもOKという広い範囲で企画を提出できることになっていたのです。ただ、星新一氏の作品などは、もうやっていないエピソードが少なくなっていたりもしたので、原作リサーチはとても大変だった記憶がります。ただ、エピソードのアイデアとして求められていることは昔と今でも変わらないと思っています。それは何かというと…
●設定・世界観の斬新さとインパクト=面白い!怖い!奇妙!
これに限ります。つまり、企画書の段階で「タイトル」だけで観たい!と思う。
※ログラインだけで引き込まれる!インパクトがあって興味をそそられる!
ということが大事ということです。
※ログライン…脚本用語で、物語全体のストーリーを2~3行で短く完結にまとめた文章。要するにオチまでつけた短いあらすじと思っていただいてOKです!
例えば、番組エピソードの一つで「墓友」という作品があります。
その時代は、「メル友」「趣味友」といった言葉が流行していたこともあり、「墓友」というタイトルのインパクトが素晴らしく、名作の一つとして人気です。他には、レジェンド脚本家の北川悦吏子さんが生み出した「ズンドコベロンチョ」も名作として語り継がれています。まったく意味不明な言葉(タイトル)ですがインパクトが強く興味を引きますよね。
当番組のエピソードとしては、やはり「引き」というのがポイントとされていますので、設定の面白さや主人公が陥るシチュエーションの面白さ、斬新さ、奇妙さ、怖さ、を打ち出すことが勝ち道といえるのです。というと、かなり乱暴な言い方ですが…。ただ、ホラーや不思議な話というのは、得てして、オチや工程がある程度いくつかのパターン、フォーマットにハメ込むことができてしまうという性質があるのもまた事実なのです。
●墓友 → 墓友という絆(設定)→相手が狂気に満ちたストーカー化(ヒトコワ)パターン
●ズンドコベロンチョ→「ズンドコベロンチョ」という謎のワード国民的流行になっている(設定)
→「言葉」に翻弄されて自滅する(不幸になる)パターン
●時間よとまれ→くしゃみをすると数十秒時間を止めれる能力が開花。特殊能力開花(設定)
※ルールあり数十秒という時間の枷(制限・ルール)
→能力の使い方を間違える(突発事故的に能力発動)自滅する(不幸になる)
=能力過信パターン
特殊能力パターンの他例:BORDER:事件被害者の幽霊が見えて会話ができる能力開花
●ランドリー→願ったモノが出てくるコインランドリーを発見。願い(欲望)が叶う(設定)
※ルールあり(主人公は知らない)
→使い方を間違えて自滅する(不幸になる)パターン
欲望が叶うパターンの他例:デスノート:名前を書くだけで相手を殺せるデスノートを入手
このような例の他にもいくつかのパターンやフォーマットが思い浮かぶのではないでしょうか?
言い方を変えると、「世にも奇妙な物語」のエピソードは、キャッチーな「タイトル」と「設定」「シチュエーション」のどれかが思いつきさせすれば、流れやオチはこれまで使われてきたパターンやフォーマットに当てはめれば成立させることができるともいえるのです。
という風に言うのは簡単ですね…。以上のことから紐解いていくと、言い方は悪いのですが、フォーマットやパターンが使いまわされており、設定がハマらなければ、既視感があり「ああ、このパターンね」というような印象を与えてしまい物足りないと判断されてしまっているということも名作が生まれにくい要因なのではないでしょうか。
テクノロジーの発展による弊害
名作が生まれにくくなっている要因の一つとして挙げられるのが「テクノロジーによる弊害」です。
これについては「世にも奇妙な物語」だけの話ではなく、ドラマや映画も含めたエンタメ全体に言えることでもあります。簡単にいうと、便利になりすぎて、人と人が接触することが容易になり、距離の壁が突破われていて、感情的な人間ドラマが描きにくくもなっている、ということです。
昭和世代から前の時代を生きてきた方には特に共感できる部分が多いのかとも思いますが、第一に人と人が簡単に繋がれることで、その間に起こったであろう人間ドラマや感情の揺らぎがすっ飛ばされてしまうということ。
昭和の名作と呼ばれる作品の中には、例えば、遠距離恋愛をテーマにしたラブストーリーだとしたら、視聴者はどこに共感して感情移入するかとイメージしてみてください。
自分や相手の家族が聞いているかもしれないけど、会えない分、声が聞きたいと思い、固定電話でコソコソと恋人に電話をかけるドキドキ感。
今、この瞬間に相手はだれと何をしているのだろう?と想像してソワソワする感覚や葛藤。
例えば、なにか事故に巻き込まれた場面ではどうでしょう?
昔は、だれもスマホなんて持っていない。公衆電話を探すか、近くの商店や民家に駆け込んで救急車を呼んでくださいと家主にお願いするところから始まり、家族や恋人に状況が伝わる伝達スピードは現代とは比べ物にならないくらいに遅かったはずです。
現代ではテクノロジーが発展したおかげで、無駄を省けることで、よりスピーディーにストーリーを展開することができ、力を入れたいシーンやカットに集中していけるというメリットもあります。ですが、逆に、本来ならもっと丁寧に重工な感情の葛藤や人間ドラマが描けた可能性の部分がなくなってしまったとも考えられるのです。つまり、人間同士の「物理的な距離」、「気持ちの距離」が近づいたことでの人間ドラマや感情の葛藤が描けなくなっているということも、名作が生まれにくくなった要因であるともいえるのです。
Z世代・α(アルファ)世代の映像視聴文化とその弊害
名作が生まれにくくなっているまた他の要因も考えてみましょう。先に述べた、テクノロジーの発展による距離の問題とも似ている部分はあるのですが、若い世代の映像視聴文化の変化(進化)の弊害も名作が生まれにくい要因といえるのではないでしょうか?
次世代の映像視聴の傾向として、ショート動画のような、完結で分かりやすい、良いとこ取り、インパクトや結論だけで、その過程やドラマは興味が薄い、ということが言えるのではないでしょうか。悪い言葉では「消費文化」「垂れ流し文化」などと言われることもありますが、特にZ世代・α世代でくくられる若い方々は、やりたいことがある程度できる環境であり、より効率的で合理的な考え方をする人が多い印象があります。なので、言い方を変えると、一つのことに集中する時間がなんだかもったいない感じがして、見たいところだけ見れれば満足。知りたい部分を知れれば満足。ということにもなるのかなと感じるのです。
そういったことから、テレビ離れが進んでいたり、ショート動画がメインになりつつあること、また、音楽もサビが好き、イントロが好き、と好きなポイントが細分化してピンポイントで消費されるといったことが散見されているのではないでしょうか。勿論それだけが理由というわけではありませんが。
映像クリエイターをしていると、そういった次世代の方々と接してお話をする機会も多いので、いろいろ質問をしてみたりもするのですが、ある方は、映画や動画は基本的に1.5倍速で観て、見たい部分だけ通常再生にして効率的に観て楽しんでいる、という方も少なくありません。テレビドラマも、CMがうざいからNetflixなどの配信で全話出揃ってからまとめて観ることが多いという方もいました。オンタイム(リアルタイム)で毎週楽しみにしながら視聴するという方はそれほど多くなく、よっぽど好きな俳優が出ていて同じ趣味や同担の友達との話題のためだけに視聴しているという方もいました。
つまり、次世代の方々は非常に賢くて能力が高いので、やりたいこと・やることが多いこともあり、タイパ・コスパを重視する傾向が強いという印象があります。よっぽど興味を持って夢中にさせられるようなインパクトやビジュアル的魅力がある作品でないとじっくりと視聴をしてもらえず、作品の良さを理解してもらうことが難しい状況にあると感じるのです。ショート動画は1分以内に結果やオチが分かる性質がりますし、非常に満足感が高いと思いますよね。
「世にも奇妙な物語」が求めているモノ=次世代視聴者が求めているホラー・奇妙
以上のことから、世にも奇妙な物語の制作陣も分かりやすく短時間で楽しめるショートホラーのコンテンツを作ったり、設定の面白さ・怖さ・奇妙さを打ち出して、という作り方を勧めているのだと想像します。
作り手側・作家側の立場で言うと、物語の結末(結果・オチ)に行くに至るまでの人間ドラマや感情の葛藤まで想像して共感してもらいたいと願う部分もありますし、とはいえ、それを昭和時代のラーメン屋頑固オヤジみたいに押し付けるのも違うと思うのです。
世にも奇妙な物語を書いてみたいと思っている作家の皆様、また、ホラーやオリジナルの怪談を考えて作ってみたいという作家の皆様、これからのホラーは設定の面白さ・斬新さ・インパクトが重視される流れになって来そうだなと、頭の片隅に置いておきつつ、素晴らしい作品を作っていってください。
そして、最後に現実的なお話をして締めくくります。世にも奇妙な物語のエピソードの脚本を書きたい!採用されたいと希望する方へ向けて下記の方法を試していただくとチャンスが広がるかと分析します。※確実とは断言できませんが、可能性があるという意味合いでご理解くださいませ。
●フジテレビか世にも奇妙な物語公式サイトに直接企画書やシナリオを郵送する。
当番組制作はフジテレビ、制作著作は共同テレビです。担当プロデューサー名を調べるなどして問い
合わせてみるのも良いと思います。
●番組募集コンペに入り込む
私が所属していた作家マネジメント事務所エム・エーフィールドをはじめ、企画募集の案内を受けて
いる脚本家をマネジメントしている会社や事務所に所属してコンペにチャレンジする。会社や事務所
はネット検索で調べられると思いますで、担当の方に「世にも奇妙な物語」を書きたい!と希望して
おくのを忘れずにいてください。
●フジテレビヤングシナリオ大賞をメインにホラー系・オカルト系のコンクールに応募する
フジテレビヤングシナリオ大賞は応募ジャンルは自由となっているので、より世にも奇妙な物語に
ハマる作品で応募することも良いと思います。最終審査の審査員にはドラマプロデューサーもいま
すし、以前、受賞者の作品を世にも奇妙な物語にマッチした内容にリライトしてもらおうかという
提案をしたというエピソードを聞いたことがあります。また、フジテレビのコンクールでなくても、
ホラーやオカルトジャンルに特化したシナリオコンクールに応募することで目に留まる可能性も
十分にあります。理由としては、企画出しメンバーに入っているプロデューサーやディレクター、
作家の皆様は原作探しにも動いているので、そういった方の目に留まる可能性も高いからです。
他にも、シナリオ投稿サイトで発表し続けたり、自分で発信する、というようないろいろな方法があるので、情熱をもって行動していただくことが一番大切なことかと思います!今回は「世にも奇妙な物語」についてお話しました。最後まで読んでいただきありがとうございます!
